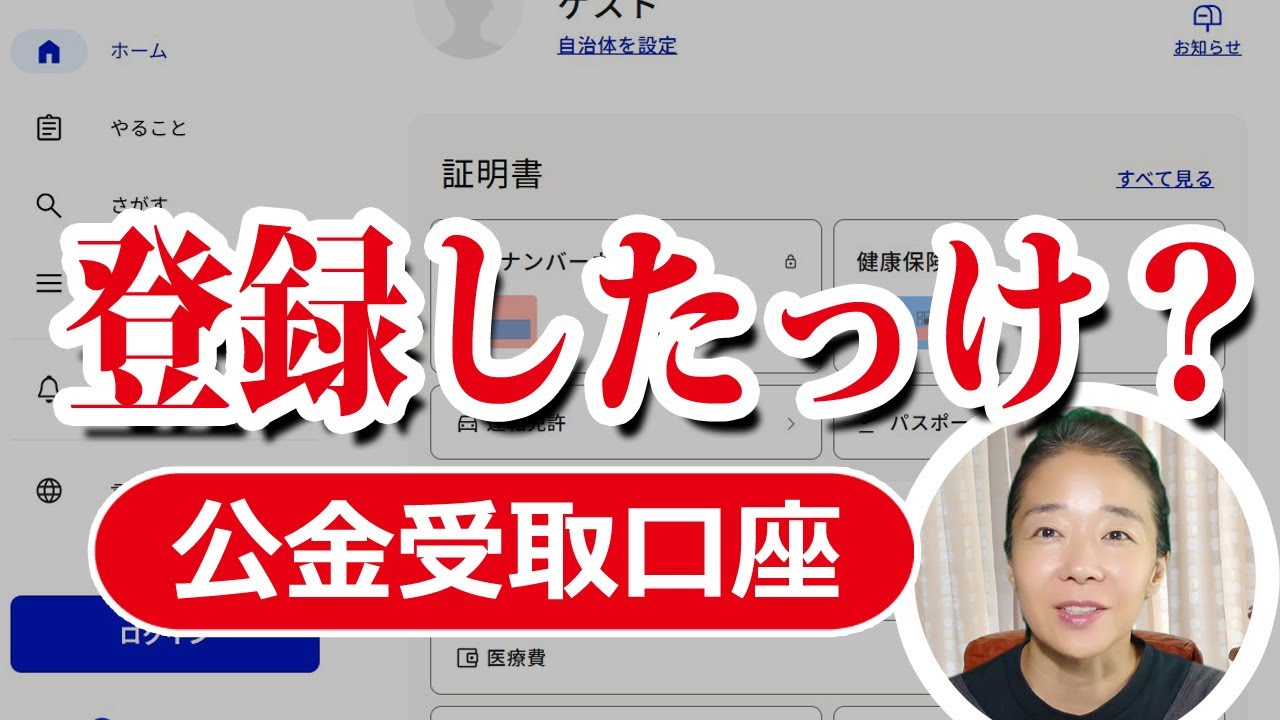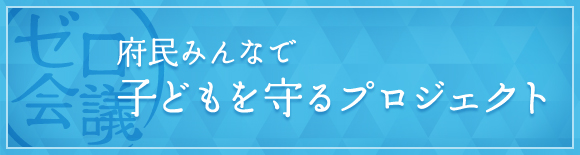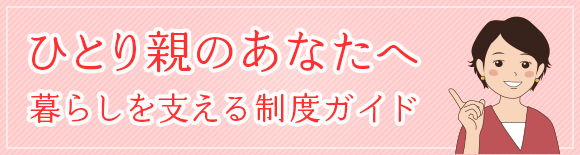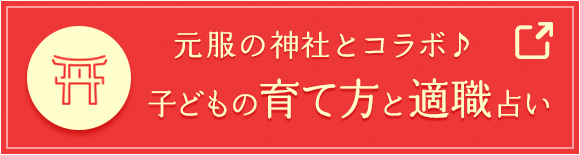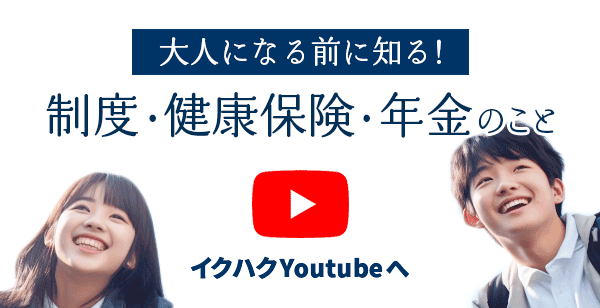公金受取口座とは?登録方法・メリット・注意点をわかりやすく解説

公金受取口座は、給付金や年金などの公的なお金を、事前に登録した銀行口座へスムーズに受け取れる仕組みです。登録方法やメリット、注意点をわかりやすく紹介します。
この記事は、社会福祉士 安木麻貴が監修・執筆しています。
公金受取口座とは?
公金受取口座とは、国や自治体から支払われる給付金、年金、税還付金などの公的資金を、直接振り込むための銀行口座です。
マイナンバーと紐づけて登録することで、申請時に口座情報を繰り返し提出する手間が省け、迅速な給付が可能になります。
公金受取口座を持つには、マイナンバーを持っていることが必須条件です。
公金受取口座を動画で解説(約5分)
公金受取口座を動画で制度に詳しい社会福祉士が分かりやすく解説しました。
登録すると何ができる?メリット3つ
- 1.手続きが簡単になる
給付金や助成金の申請時に口座情報を再提出する必要がなくなります。 - 2.給付が早くなる
登録済み口座に自動で振り込みが行われるため、審査後すぐに受け取れます。 - 3.誤入力リスクの低減
口座情報を繰り返し入力する必要がないため、記載ミスによる振込遅延が減ります。
また自治体にとっても、振込作業に必要な莫大な経費(人件費)の削減になります。
●公金受取口座を持つ方の感想
コロナの給付金の時に登録しました。その後も利用していますが、給付金によってはこの口座があるのにいちいち振込口座の申請が必要なものもあり、混在しているのが不便です。一元化を望んでいます。(イクハクSNSより)
●公金受取口座を持たない方の感想
民間の銀行口座と、公的なマイナンバーとが紐付けられるのが管理されているようで抵抗がある。(イクハクSNSより)
公金受取口座を確認する方法
●マイナポータルで確認(スマホ・PC)する場合
※スマホやPCでログインする場合は専用アプリを入れていないと見られません。
※マイナポータルとは、マイナンバーの情報を閲覧するための公的なウェブサイトです
1.マイナポータルにアクセス
2.マイナンバーカードでログイン
・スマホはNFCでのカード読み取り
・PCはICカードリーダーを使用
3.メニューから「公金受取口座の登録・変更」を選択
4.登録状況が表示される(登録済みなら銀行名・支店名・口座番号の一部が表示)
●マイナポータルで確認している人の感想
専用アプリのインストールは高齢者には難しいと感じました。私は娘に頼んで入れて貰いましたが、本来は人にやってもらうものではありませんよね。(イクハクSNSより)
●市区町村窓口で確認する場合
1.マイナンバーカードと本人確認書類(必要に応じて)を持参
2.担当窓口で「公金受取口座の登録状況を確認したい」と伝える
3.担当職員がシステムで照会し、登録有無を教えてくれる
登録できる人と対象口座
登録できるのは、日本国内に住民票を有し、マイナンバーを持つ人です。
対象となる口座は、本人名義の銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などの普通預金口座です。家族名義や法人名義の口座は登録できません。
登録方法と手順
登録は、マイナポータル(スマホ・PC)または市区町村窓口から行います。
1.マイナポータルへログイン(マイナンバーカード+暗証番号が必要)
2.「公金受取口座の登録」メニューを選択
3.金融機関を選び、口座番号を入力
4.登録内容を確認し、送信して完了
※市区町村窓口では、「公金受取口座の登録」をしたいと伝えてください。身分証の提示が必須です。
登録後に変更・解約する場合
引越しや銀行変更などで口座を変更・解約したい場合は、同じくマイナポータルや市区町村窓口で手続き可能です。
よくある質問
-
公金受取口座は必ず登録しないといけませんか?
-
義務ではありませんが、登録しておくと給付金受取がスムーズになります。
-
自分が公金受取口座に登録しているか分からない
-
マイナポータルで確認するか、市区町村窓口のどちらかで確認できます。
-
どんな給付金が公金受取口座に振り込まれますか?
-
年金、児童手当、臨時給付金、税還付金など多くの公的給付金が対象です。
-
口座登録に手数料はかかりますか?
-
無料です。登録や変更、解約にも費用は発生しません。
-
家族の口座を登録できますか?
-
できません。本人名義の口座のみ登録可能です。
-
口座登録に手数料はかかりますか?
-
無料です。登録や変更、解約にも費用は発生しません。
-
登録後に別の口座に振込を受けたい場合は?
-
マイナポータルまたは窓口で変更手続きを行います。
-
口座が間違って登録されていた場合はどうなりますか?
-
振込ができず、自治体や国から連絡が来ます。正しい口座を再登録してください。
関連語句

Written by 安木 麻貴
社会福祉士 | 育児制度アドバイザー
社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、多くの子育て世帯から信頼を得ている。