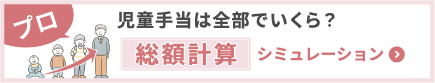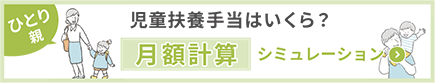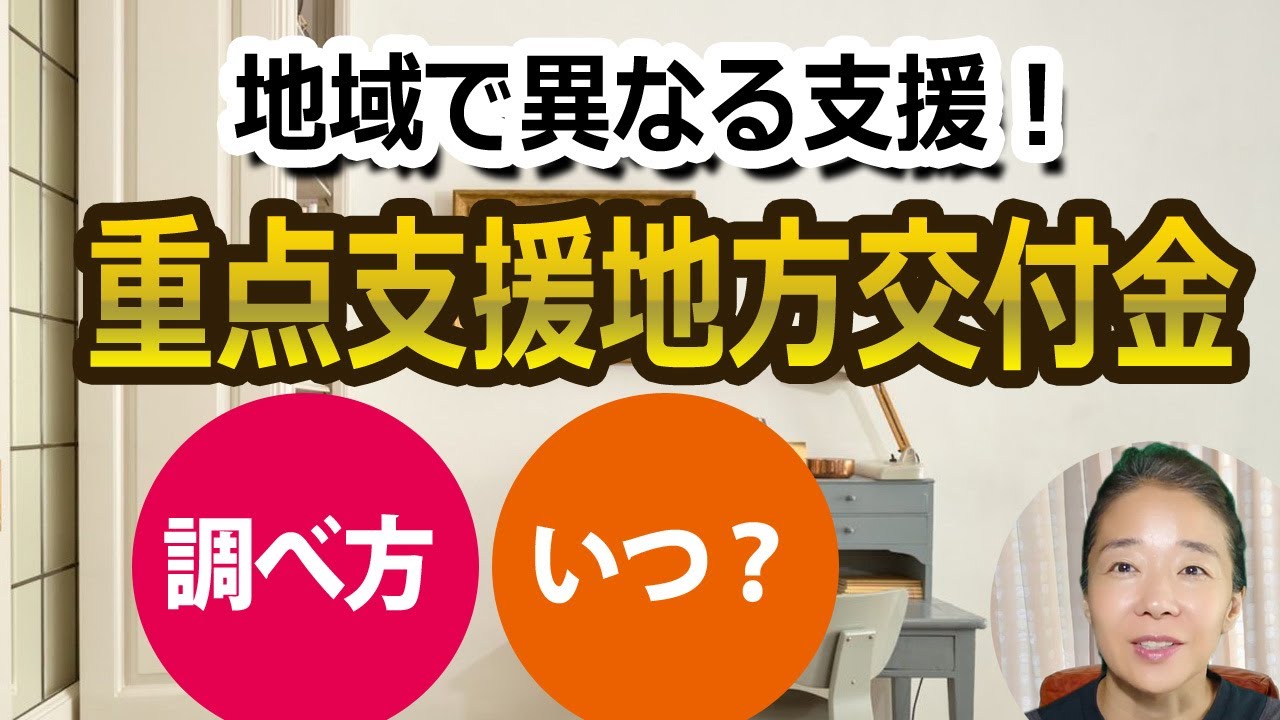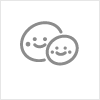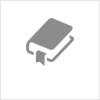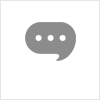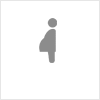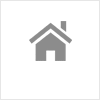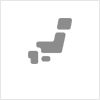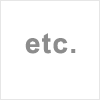重点支援地方交付金を活用した【自治体別】物価高対策・給付金の調べ方を解説。住民税非課税世帯や子育て世帯向けの支援内容、実施中の自治体施策をわかりやすく紹介します。
- お金
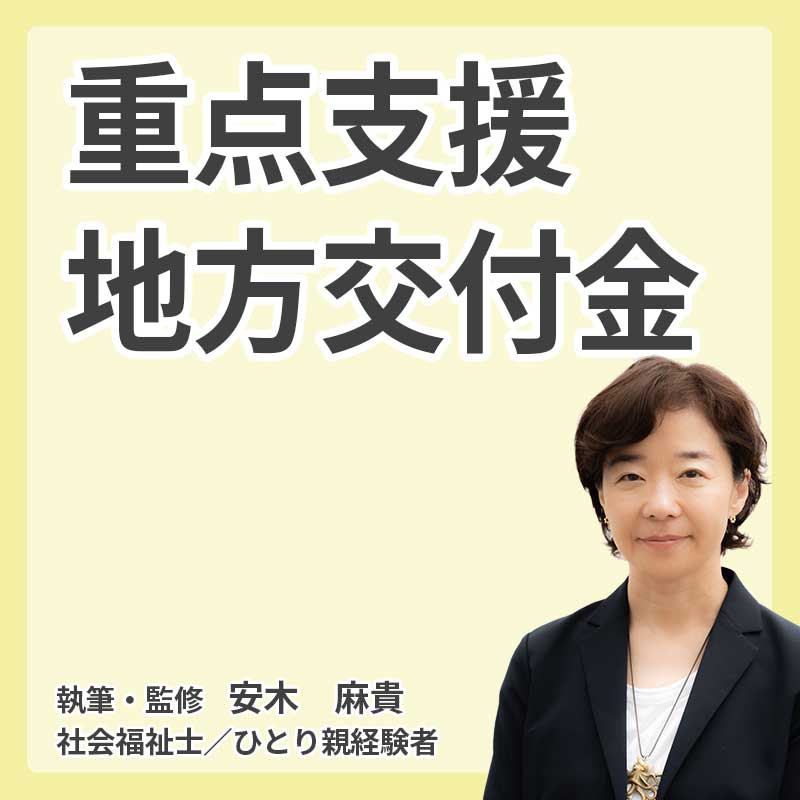
【2026年最新・自治体別】物価高対策・給付金の調べ方|重点支援地方交付金とは
現在、物価高対策として全国の自治体で給付金や支援事業が実施されています。
これらの多くは、国の「重点支援地方交付金」を活用して行われており、実施内容や支援額は自治体ごとに異なります。
このページでは、「自分の地域で、今年(2026年)受けられる物価高対策を調べる方法」を自治体の事例をもとにわかりやすく解説します。▶ あなたの地域の物価高対策をすぐに調べる
例:
「〇〇市 物価高対策」
「〇〇区 給付金 2026年」
「〇〇町 重点支援地方交付金」上記のように 自治体名+キーワード で検索すると、公式ページが確認できます。
目次自分の地域の物価高対策・給付金を調べる方法【自治体別】
お住まいの自治体の重点支援地方交付金活用内容に関する自治体のホームページは順次開設していくことになります。
そこで、お住まいの自治体(役所)の実施状況を調べる方法をお伝えします。調べ方①お住まいの自治体のホームページから該当ページを探す
各自治体では、物価高対策として重点支援地方交付金を活用した内容のページが掲載されていきます。
ですので、お住まいの自治体のホームページにアクセスし、検索窓に「物価高対策」と入力して該当ページを見つけてください。(下記に検索窓入力画面の例を記載してあります)
該当ページに対象者や物価高対策の内容と時期が記載されていきます。
※ネットで「お住まいの市区町村名+重点支援物価高対策」と検索してもヒットする場合があります。
例:「〇〇市 物価高対策」「〇〇区 給付金 2026年」「〇〇町 重点支援地方交付金」
※専用のコールセンターも順次開設していくと思いますので、電話で状況などお問い合わせください。調べ方②自治体ホームページにページが無い場合は、役所に電話してみる
自治体のホームページに記載が無い場合、ネットが繋がらない環境にある場合は、市区町村役所・役場の代表番号に電話して、 「物価高対策」について知りたいので、つないでください」と伝えて、支援の内容や対象者を聞いてみましょう。
重点支援地方交付金で実施されている物価高対策とは
重点支援地方交付金とは、物価高騰による生活への負担を軽減するため、自治体に自由度の高い財源を提供する制度です。
地域ごとの実情に応じて活用できる点が特徴で、自治体は国へ申請した上で事業を実施します。
食料品の高騰対策から子育て支援や低所得世帯の支援まで、幅広い支援に活用できる仕組みとなっています。各自治体の物価高対策の主な支援内容(給付金・子育て世帯・非課税世帯)
子育て世帯向け支援がある自治体
「〇〇市 給付金」「〇〇市 物価高対策」などで検索すると、自治体公式サイトで最新の支援内容を確認できます。
*福島県 郡山市:子ども1人あたり2万5000円の子育て応援手当を支給
・実施時期:2026年3月から支給開始
*福島県 いわき市:①児童一人当たり2万円の子育て支援手当に、1回限り1万円を加算。②水道基本料金の来年2~5月請求分の減免
・実施時期:未定
*茨城県: 低所得の子育て世帯向けに、県独自に児童1人当たり5万円を支給する。対象は児童扶養手当を受給するひとり親世帯や住民税非課税の低所得世帯。
・実施時期:未定
*東京都 府中市:0歳から18歳までのお子さま1人当たり1万円分のデジタルギフトを支給。
・実施時期:2025年12月5日までに発送
*石川県 金沢市:①非課税世帯に、1世帯あたり3万円を給付。②子育て応援手当は、国の応急手当に1万円を上乗せした3万円を支給。③水道基本料金の無償化期間を2か月延長し4か月間とする。
・実施時期:2026年3月から順次
*山梨県:①18歳以下の子ども1人あたり2万円を上乗せ給付=国の分とあわせるとあわせて4万円が支給。②生活困窮世帯への支援として臨時的に一人あたり3000円のお米券を配布。
・実施時期:各市町村別に実施
*香川県 高松市:①児童手当の対象者を除く約35万人に1人当たり5000円を給付。②市立の小中学校などの3学期の給食費を無償化。
・実施時期:2026年3月までに
*高知県: 小中学校の給食費や保育料などそれぞれ2カ月分を免除し、低所得のひとり親世帯に児童1人あたり2万円を給付する。
・実施時期:未定
*福岡県 直方市:小中学校の学校給食費と幼・保・こども園の副食費(おかず代)について、来年1~3月分を無償化する。
・実施時期:2026年1~3月住民税非課税世帯向け支援が中心の自治体
「〇〇市 給付金」「〇〇市 物価高対策」などで検索すると、自治体公式サイトで最新の支援内容を確認できます。
*北海道 函館市:住民税の非課税世帯に対して3万円の現金給付。
・実施時期:未定
*東京都 江戸川区:住民税の非課税世帯に対して3万円の現金給付。
・実施時期:2026年1月~
*京都府 京都市:住民税非課税世帯に対しては1世帯あたり5千円の現金給付する予定。
・実施時期:2026年5月~
*兵庫県 明石市:ひとり親世帯向けには、児童扶養手当などの受給資格者に児童1人当たり1万円を支給する。
・実施時期:2026年2月~
*福岡県 北九州市:非課税世帯に1万円給付
・実施時期:2026年3月までに
*広島県 廿日市市:市民全員に対し1人当たり3000円、住民税非課税世帯にはさらに追加で1人3000円を給付する。
・実施時期:2026年2月下旬~
*沖縄県 那覇市:住民税非課税世帯と、課税標準額100万円以下の人に「おこめ券」配布。
・実施時期:2026年1月末~市民(所得制限なし)の自治体
「〇〇市 給付金」「〇〇市 物価高対策」などで検索すると、自治体公式サイトで最新の支援内容を確認できます。
*北海道 札幌市:全市民対象に1人3000円の支給(お米券や電子マネーでの支給)
・ 実施時期:2026年3月までに
*秋田県:1万2,000円分の利用券を1万円で購入できる「電子チケット」
・実施時期:2026年3月から利用予定
*山形県 川西町:町内の店舗で使用できる1人あたり7000円分の商品券をすべての町民に配布予定。
・実施時期:未定
*宮城県 仙台市:1ポイント1円で利用できるみやぎポイント3000円分を市民に支給。
・実施時期:2026年1月から支給予定
*宮城県 名取町:①デジタル地域通貨「なとりコイン」を市内全世帯に1万円分ずつ配る。②水道基本料金の3カ月減免。
・実施時期:未定
*新潟県 新潟市:市民1人あたり3000円の現金給付。
・実施時期:5〜6月を目途に計画
*東京都 東村山市:市民1人あたり4000円給付
・実施時期:2026年3月までに
*東京都 東久留米市:PayPayアプリから1,000円分のプレミアムが付いた4,000円分の「東くるめプレミアムデジタルチケット」を3,000円で購入。
・実施時期:2025年12月15日から
*神奈川県 横須賀市:市民全員に現金6千円を給付する。
・実施時期:2026年2月~
*静岡県 浜松市:6000円分の商品券を3000円で1人3口まで購入可能。
・実施時期:2026年6月から販売
*石川県 野の市市:「おこめ券」を市民1人当たり4400円相当で配る。
・実施時期:未定
*大阪府 大阪市:1万円の購入で1万3000円分の買い物ができる「プレミアム付商品券」を発行。
・実施時期:未定
*和歌山県 和歌山市:全市民を対象に6000円分の地域商品券の発行。
・実施時期:2026年3月中旬から発送
*岡山県 岡山市:全ての市民に1人あたり現金3000円を給付。
・実施時期:2026年2月から順次支給
*山口県 防府市:市民全員に「おこめ券」3千円分を支給する。米以外にも使える商品券2千円分もあわせて給付する。
・実施時期:2026年春を予定
*島根県 浜田市:プレミアム付「はまだ応援チケット」の発行。1冊7000円のプレミアム券を5000円で販売。
・実施時期:未定
*愛媛県 松山市:3000円で6000円分の買い物ができるプレミアム付商品券を発行。
・実施時期:2026年4月の利用開始
*福岡県 福岡市:①家庭の下水道使用料を2か月分無料にする。②福岡商工会議所や商店街が発行するプレミアム付商品券事業。
・実施時期:2026年3月までに
*大分県 大分市:1冊1万円で1万3000円分の買い物ができる商品券を販売。
・実施時期:2026年6月から利用開始
*大分県 別府市:1冊5000円で7500円分の買い物が出来るプレミアム率50%の商品券。
・実施時期:2026年4月から利用開始
*熊本県 熊本市:1万円分の商品券を購入した場合、1万4000円分の買い物ができる商品券発行。
・実施時期:2026年3月までに実施時期はいつから?
自治体は国へ申請後に事業を開始します。多くの自治体は2026年3月までの実施を目指しています。
具体的な開始日は自治体ごとに異なるため、住民向けの広報や自治体公式サイトの発表を確認する必要があります。国が示す推奨メニュー
国は自治体が実施しやすいよう、重点支援地方交付金の活用メニューを提示しています。
① 食料品の物価高騰対策(特別加算)
・プレミアム商品券
・電子クーポン
・地域ポイント
・おこめ券
・現物給付
② 低所得者世帯・高齢者世帯への支援
・現金給付
③ 子育て世帯への支援
・給付金
・学校給食費の補助
・子育て関連サービスの負担軽減
④ 生活インフラの負担軽減
・水道料金の減免
・LPガス使用世帯への給付金
・公共施設の利用料減額
⑤ 省エネ家電の買い換え支援
・省エネ性能の高いエアコン・給湯器への買い換え補助重点支援地方交付金の解説動画(04:20)
重点支援地方交付金を制度に詳しい社会福祉士が、わかりやすく動画で解説します。
重点支援地方交付金の使い道
重点支援地方交付金は、自治体が住民のニーズに応じて多様な支援に活用できます。主な使い道としては以下のとおりです。
・低所得世帯や子育て世帯への給付金
・食料品価格高騰に対応する「お米券」「電子クーポン」などの配布
・学校給食費の補助や、こども食堂・ヤングケアラーへの支援
・自治体施設の水道料金の減免
など国が一律の対策を決めるのではなく、地域の課題に応じて自由に設計できることが最大の特徴です。どんな支援が期待できる?
重点支援地方交付金の拡充により、特に子育て世帯や生活に負担を感じている世帯を中心に、以下のような支援が期待されています。
・食品購入の負担軽減(クーポン・商品券配布)
・給食費の軽減や子育て世帯の支援強化
・高齢者や低所得世帯への給付金の拡充
・生活インフラ費用の軽減(例:水道料金減免)
・省エネ家電への買い換えに伴う家計負担の軽減
自治体によって支援内容は大きく異なるため、最新情報の確認が重要です。よくある質問|Q&A
重点支援地方交付金は全国どの自治体でも実施されますか?
全国すべての自治体に交付されますが、実施する支援内容は自治体ごとに異なります。
給付金の受け取りには申請が必要ですか?
自治体によって申請が必要な場合と自動給付の場合があります。自治体の案内を確認してください。
食料品クーポンは誰でも受け取れますか?
対象者は自治体が決定します。低所得世帯や子育て世帯を対象とするケースが多いです。
省エネ家電の買い換え支援は対象家電が決まっていますか?
国が示すメニューを参考に、自治体が対象家電を指定します(エアコン・給湯器など)。
自分の自治体の実施内容はどこで確認できますか?
自治体のホームページや広報誌などで順次案内されます。
まとめ
重点支援地方交付金は、物価高騰の影響を受ける生活者への支援を強化するため、自治体が自由に活用できる財源として拡充されました。食料品の高騰対策や低所得世帯支援、子育て支援など、地域の実情に応じた多様な支援が可能になります。実施内容や開始時期、申請の有無は自治体によって異なるため、「自分の住んでいる自治体でどのような支援が行われるのか」を早めに確認することが大切です。
本記事は、全国共通の制度説明ではなく、「自分の自治体で今受けられる物価高対策を調べるためのナビページ」です。この記事の参考資料・出典
・内閣府:「強い経済」を実現する総合経済対策
Written by 安木 麻貴
社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。特に子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、保護者目線での配信内容が多くの子育て世帯から信頼を得ている。