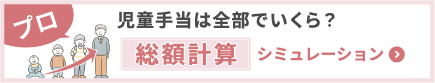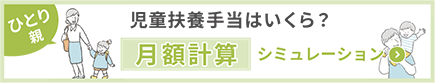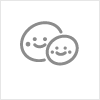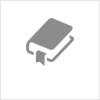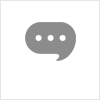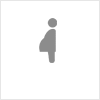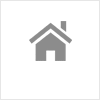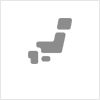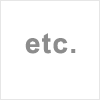20歳から50歳未満の方で、所得が低い場合は国民年金の納付が猶予される
- お金
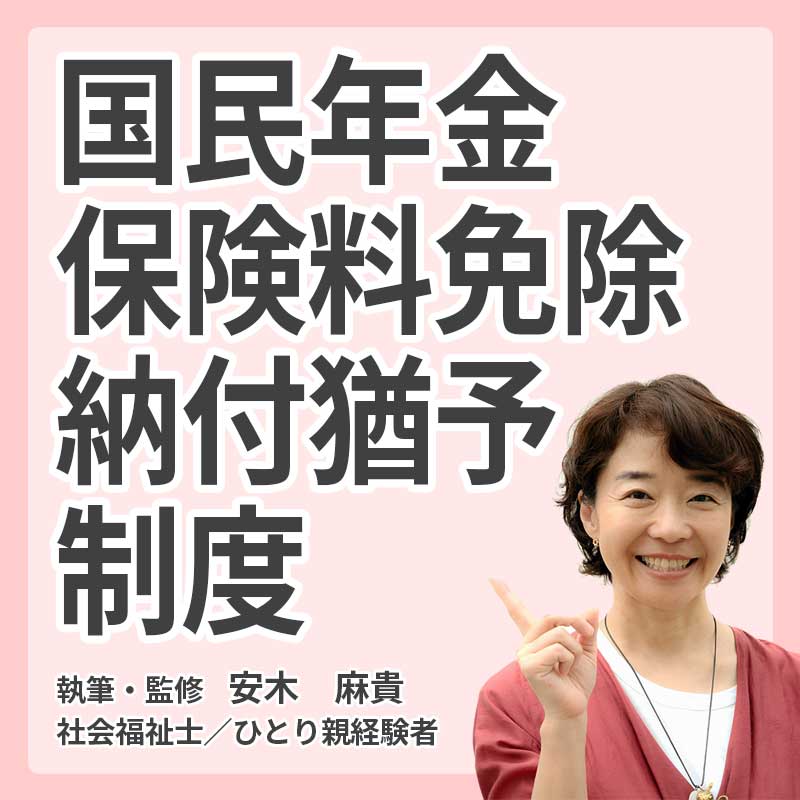
国民年金保険料納付猶予制度
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
ここでは、 国民年金保険料納付猶予制度のメリットやよくある質問などをわかりやすく解説します。目次国民年金保険料納付猶予制度とは
国民年金保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年間)には算入されます。
年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。【関連語句】
・所得
手続きをするメリットは?
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
〇失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。 問い合わせ先や申請書類受け取りは年金事務所ですが、提出先は各市区町村役場です。
〇お住まいの年金事務所を探す場合はこちら
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html国民年金保険料納付猶予制度 よくある質問
国民年金保険料納付猶予制度の納付猶予とはどのようなことですか?
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの 障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
※「猶予」とは、すぐにもそれをしなければならない人に対し、実行時期を先送りし、余裕を与えること。国民年金は10年以上たってから追納することはできませんか?
納付期限から10年以上過ぎている場合は、追納ができません。
この場合は、60歳から65歳未満までの5年間にわたって国民年金の任意加入をすることで受給資格期間・保険料納付済期間を増やすことができます。国民年金保険料納付猶予制度の申請は毎年必要ですか?
申請は、原則として毎年度必要です。 ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望し、「希望する」を選択した場合は、継続して申請があったものとして継続審査を行います。
国民年金保険料納付猶予を受けました。どのように追納したらいいですか?
猶予を受けていた期間の国民年金保険料は、厚生労働大臣の承認を受け、その承認がされた月の前10年以内の期間のものに限り、後から納付することができます。これを、「追納」と言います。
追納の方法は、まず、お住まいを管轄する年金事務所の窓口に、国民年金保険料追納申込書をご提出して、後日、専用の納付書が届いたら金融機関などで納付する流れになります。
詳しい内容については、お住まいの年金事務所に問い合わせしてみてください。この記事の参考資料・出典
・日本年金機構:国民年金保険料納付猶予制度の実施要項
生活が苦しいとお悩みの方に対しての関連制度
進学に向けての経済的な支援制度を知りたい方へ
Written by 安木 麻貴
社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。特に子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、保護者目線での配信内容が多くの子育て世帯から信頼を得ている。